毎月の基本給に加えて、さまざまな「手当」を支給している企業も多いのではないでしょうか。
手当を充実させることは、従業員のモチベーション維持や向上にも大きく影響します。
この手当ですが、実にさまざまな種類が存在します。
今回は、この「手当」の種類や特徴について、詳しくご紹介をしていきたいと思います。
目次
「手当」ってなに?
概要
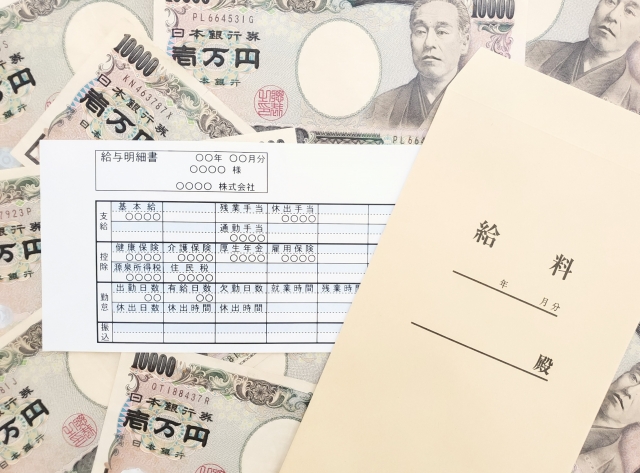
これは、「諸費用として基本給と併せて支払う賃金」のことを指しています。
手当を支給する目的としては、「職員のモチベーションの維持・向上」そして「必要経費を会社が補填する」といったケースが多いかと思います。
また、手当は「給与」に含まれるのですが、税金や社会保険料などについて、基本給とは異なる扱いを受ける場合もあります。
ちなみに、「基本給」と「手当」には、以下のような違いがあります。
◆「手当」 :経費の補填等のために支給する、付加的なもの
このことから、一部の手当については、割増賃金の計算の基礎から除外されます。
手当というのは「経費を補填するなどの目的で支給するもの」であるため、基本給とは分けて支給していると考えると、わかりやすいかもしれません。
手当には2つの種類が存在する
上記でもご紹介した通り、手当というのは“基本給以外に支払われる賃金”のことを指しています。
そして、手当は「法律上、支給しなければならない手当」と「会社側が任意で決める手当」の2種類に大別することができます。
この「法律上、支給しなければならない手当」は、労働基準法で定められる以下の3つです。
◆「休日手当」
◆「深夜手当」
これらは法的な観点から該当者に支給する義務があるため、仮に支給を怠ると労働基準法による罰則が適用されてしまいます。
対して、「会社が任意で決める手当」は、手当の種類・対象・手当金算定のルールなど、会社によって異なることとなります。
給与との関係性について
基本給とは別に支払われる手当ですが、例えば以下のような手当は給与の一部と見なされて「課税対象」となります。
◆「休日出勤手当」
◆「職務・役職手当」
◆「住宅手当」 など
ただし、以下の3つの条件に関しては「非課税」となります。
②「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」
③「宿直や日直の手当のうち一定金額以下のもの」
なぜ、手当は支給されるのか?

「残業」「休日」「深夜」などの各手当は、法律で定められていることはもちろん、“労働の対価”として支払われて当然のものです。
ただ、それ以外にもさまざまな手当が存在します。
会社が任意で決める手当には、従業員の家族状況や職位・仕事内容といったさまざまな条件によって支給されますが、その目的や支給するメリットには、どういったものがあるのでしょうか?
まとめると、以下が挙げられます。
◆「給与テーブルのほかに加える、調整金として役割」
◆「啓蒙やモチベーションの向上を目指すためのもの」
手当を受け取る側としては、やはり「モチベーションの維持・向上」は大きいです。
例えば、「資格手当」。
資格にはさまざまな種類が存在しますが、取得するためには大なり小なりの“努力・時間・費用”が発生します。
やっとの思いで資格を取得したのに、「仕事量が増えるだけで収入には一切変化がない」では意味がありません。
「役職手当」だってそうです。
一生懸命努力して一定の役職に就いたのに、「仕事量が増える一方で収入にはなんの変化もない」では目も当てられません。
このように“努力に見合った成果”に一番直結するものこそが、「手当」なのです。
手当が支給されることは、従業員のやる気やスキルの向上をうながすものであり、従業員の満足度に直結するのです。
とはいえ、会社側の立場でみると「手当の支給=コストがかかる=会社の負担も大きくなる」ということに間違いはありません。
そのため、近年は(時代に合わせて)“業種との関連性の強い内容に見直される傾向にある”とはいえます。
会社は慈善事業を行っているわけではありません。
経営を「始める・維持する・発展させる」ためには、当然ながら会社側にも相応の費用が発生するため、この点にどう折り合いをつけていくかが大切になってくるのです。
「手当」と「福利厚生」の違いとは?
閲覧する求人の内容によっては、「福利厚生」の中にさまざまな「手当」が記載されていることがあります。
しかし、厳密にはこの2つは異なります。
「福利厚生」は、“すべての従業員が対象”となります。
対して「手当」は、“条件に該当する従業員のみが対象”となるのです。
上記でも記載した「資格手当」や「役職手当」などが、まさにそれです。
これらは、一定の「資格」を所持している人、あるいは一定の「役職」に就いている人が受け取れる“手当”です。
そのため、厳密には「福利厚生」ではありません。
尚、福利厚生にも、法律で定められている「法定福利厚生」と、企業が独自に定めている「法定外福利厚生」の2種類が存在します。
それぞれを例に出すと、以下のようになります。
◆「法定外福利厚生」:交通費、健康診断や人間ドック費用、育児・介護に関連するもの
さらに余談ですが、「給与」と「給料」も、厳密には意味が異なります。
簡単に説明すると、以下のようになります。
◆「給料」=基本給
※現物支給も「給与」に含まれる
「給与」は、基本給・残業代・通勤手当など、会社から金銭で支払われるものすべてを対象としています。
ボーナスやインセンティブなど“毎月固定されているわけではない報酬”も含まれますし、社宅の貸与などの金銭以外の形で与えられる「現物給与」も給与に含まれることとなります。
対して「給料」は、“給与からボーナスや各種手当などを差し引いたもの”のことを指しています。
そのため、「基本給=給料」と考えて良いでしょう。
「給与」が労働状況や会社の業績により変動するのに対し、「給料」は基本的に一定の金額が保たれます。
昇給やベースアップなどが行われない限り、「給料」の金額は変動しません。
厳密にはこの2つは意味が異なりますので、この点にも注意しておくといいでしょう。
法律で定められている手当の種類について

上項でもお伝えした通り、労働基準法で定められている手当は、以下の3つです。
◆「休日手当」
◆「深夜手当」
それぞれ、補足を加えていきたいと思います。
「時間外手当(残業手当)」とは?
労働基準法では、労働時間が「1日8時間まで、1週間で40時間まで」と定められています。
この定められた時間を超えて勤務をすると発生するのが、この手当です。
そして、この手当は以下の条件に該当する場合に支払われることとなります。
②時間外労働が限度時間(1カ月45時間、1年360時間など)を超えたとき:割増率25%以上(※1)
③時間外労働が、1か月60時間を超えたとき:割増率50%以上(※2)
(※1)25%を超える率とするよう努めることが必要である
(※2)中小企業は25%以上
尚、時間外労働を実施するには、労使間で「時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署に提出しなければいけません(義務である)。
もし締結せずに法定労働時間を超えて残業させた場合は“違法”となり、罰金などの適用対象となってしまいます。
そしてもう一つ、上記③についてです。
この割増率は本来「25%以上」だったのですが、2019年4月1日より「50%以上」に引き上げられています。
中小企業では2022年時点でも「25%以上」となっていますが、2023年4月1日からは「50%以上」に引き上げられることとなります。
「休日手当」とは?
まず、労働基準法では以下のような「法定休日」が定められています。
「週1回以上、または4週間に4回以上」
「法定休日」というのは、労働基準法35条で規定されている休日のことで、この手当は「法定休日に勤務させた場合」に支払う義務が発生します。
割増率は「35%以上」です。
「深夜手当」とは?
この手当は、以下の条件に該当する場合に支払われるものです。
「午後10時~午前5時の間に勤務させた場合」
※厚生労働大臣が必要と認めた地域や機関によっては、午後11時~午前6時となる場合もある※
割増金は、「25%以上」となります。
特に、医療や介護の業界では「夜勤」が発生することも多いため、夜勤で働く人には必ずこの「深夜手当」が支給されているのです。
法律上の手当の扱いに関する注意点について
まず、上記でご紹介した「時間外」「深夜」「休日」の各手当は、重複した場合は各手当が同時に支給されることとなります。
例えば、「時間外労働(50%or25%)」+「深夜労働(25%)」が同時に発生した場合、50%or75%の割増賃金を支払わなくてはいけません。
「休日出勤(35%)」+「深夜手当(25%)」が同時に発生した場合、両方を合算した60%の割増賃金を支払わなくてはいけません。
加えてもう一つ。
「残業手当」というのは、基本的に“基本給に加算されて支払われる”こととなります。
もし残業手当が発生している人は、給与明細表を確認してみましょう。
必ず、毎月支給されているはずです。
この手当を、「後で賞与から差し引く」「後払いにして賞与に加えて支払う」といったことは、正当な支払いとは認められていないのです。
「給与」と「賞与」は別物であるため、この点もしっかり理解をしておく必要があります。
また、残業手当には「固定残業手当」というものがあります。
この場合、必ずその条件を明記しておかなくてはいけません。
例えば、「月に20時間分の時間外手当を含む」などです。
この場合、固定残業手当の相当時間を超えることで、それに応じた残業手当が支給されることとなるのです。
最後に。
ここでご紹介した「法律で定められた手当」は必ず支給しなければなりませんが、例外として「管理職(管理監督者)」に対しては、時間外手当や休日手当は支払わなくても良いとされています。
この管理監督者の条件となるのは、以下のような場合が例として挙げられます。
◆「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない立場である」
◆「賃金等でその地位に相応しい待遇にある」
ただし、深夜手当だけは支払いが必要となります。
会社が任意で支給する手当の種類について
次に、法律で定められていない手当……つまり「会社が任意で支給する手当」についてのご紹介です。
これは、会社ごとに就業規則によって定めることができます。
一般的によく定められている手当としては、以下のようなものが挙げられるでしょうか。
◆扶養手当/家族手当
◆住宅手当
◆通勤手当
◆出張手当
◆食事手当
◆特殊勤務手当
◆皆勤手当・精勤手当
◆資格手当/研修手当
多くの人がもっとも目にする機会が多い手当は、やはり「通勤手当」ではないでしょうか。
これは、自宅から勤務先までの通勤にかかる費用を支給するものです。
公共交通機関を利用する場合は定期代などを実費で支給しますし、自動車や自転車の場合は通勤距離によって支給される場合もあります。
後は、医療・介護・保育・福祉の業界には多種多様な資格が存在し、また研修も多いため、「資格/研修手当」を支払っているところも多いかと思います。
また、会社が任意で支給する手当に関しては、時代の変化に合わせて新しいものも増えています。
例えば、数年前より蔓延した「新型コロナウイルス」の影響によってテレワーク(在宅勤務)が普及したことにより、テレワークを行う従業員に対して手当を支給する会社が増えました。
「テレワーク手当」であったり、コロナ禍でも出社せざるを得ない状況の従業員に対して「出社手当」を支給したり……です。
特に、医療・介護・保育・福祉は、人との関わりが密接に関係してくることから、「出社手当」を支給している企業も多いのではないでしょうか。
(もちろん、支給するかどうか、そして支給の仕方は会社によってさまざまです)
他にも、近年は「健康」に対する意識が社会的に高まっています。
従業員に健康意識を高めてもらうことを目的に支給されているのが、「健康増進手当」です。
非喫煙者や健康診断を受診した従業員を対象に支給したり、スポーツジムやヨガなどフィットネスを利用する際に支給しているところもあります。
これら手当を充実させることは、離職者を減らしたり、採用活動時のアピールになったりといったメリットも期待できます。
このように、時代の変化に合わせて、今後も新しい手当が導入される可能性はあるかもしれません。
まとめ
以上が、「会社から支給される手当の種類・特徴について」となります。
手当には、“法律上必ず支給しなければならないもの”と“会社の任意で支給されるもの”に大別することができます。
特に後者に関しては、企業によって手当の種類や内容が異なるため「自分が勤務しているところでは、どんな手当を・どのような形で支給されているのか?」をしっかりと把握しておいた方が良いかと思います。
手当は、給与額に直結する(働く人にとって)非常に重要な要素であり、働くモチベーションにつながるとても大切な制度です。
就職や転職を考えている人も、不明点があれば必ず事前に確認を取るようにしてください。
また、会社側にとっても、手当の種類や特徴を正しく理解し・運用していくことが、離職者の現状や従業員満足度の維持・向上などに大きな変化をもたらしてくれるはずです。
今後も、時代の変化に合わせて新しい手当も導入されるかもしれません。
最後に。
大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から「同一労働同一賃金」が適用されるようになりました。
これは、「同じ業務、同等の仕事量の正規社員と非正規社員の間で、勤務状況に差が出ないよう同じような賃金を支払う」ことです。
これまで正規社員のみにしか支払わなかった制度があれば、それは非正規社員にも支払うようにしなければなりません。
尚、これは基本給・賞与・各種手当などの「賃金」に関することだけでなく、「教育訓練」や「福利厚生」も対象となります。
会社によって就業者の状況は異なりますし、企業・職種・就労場所・勤務時間によって、条件は人それぞれで大きく異なります。
“仕事と従業員の実情にあった手当”が今後ますます求められることとなるので、変化に柔軟に対応していけるように、都度見直しを行っていくくことが大切になるかと思います。

